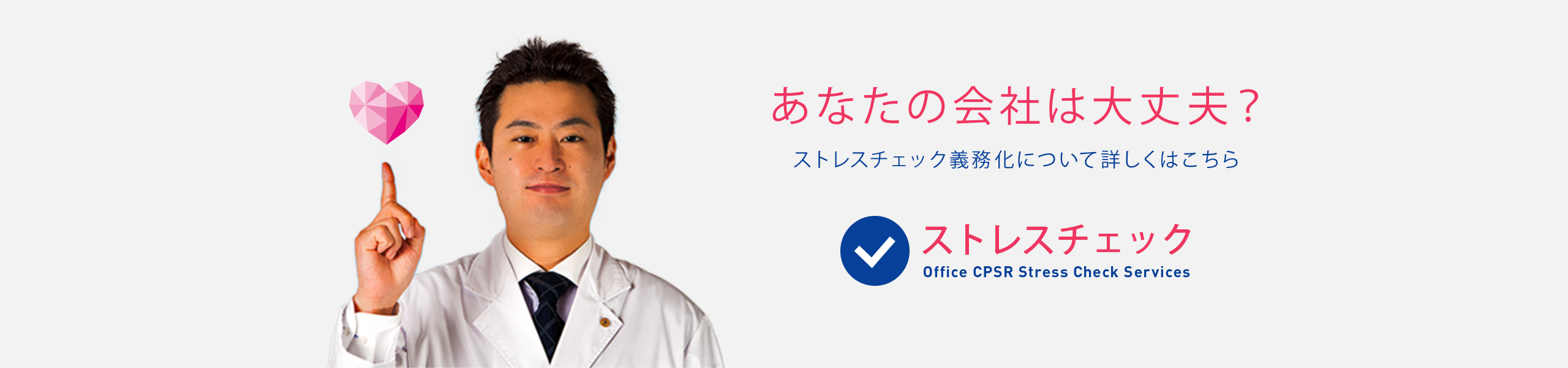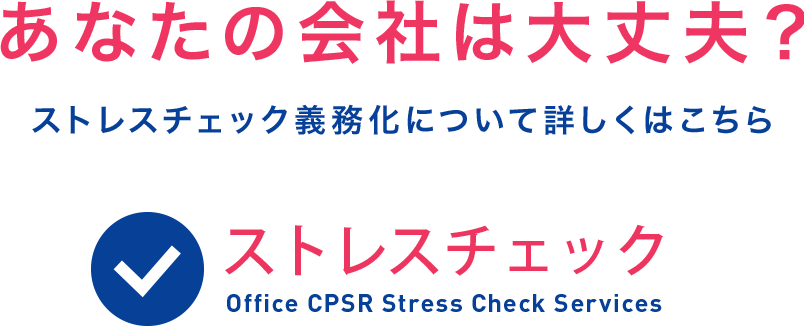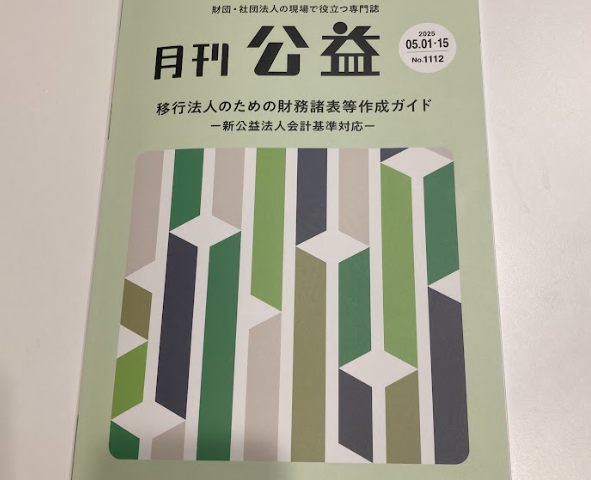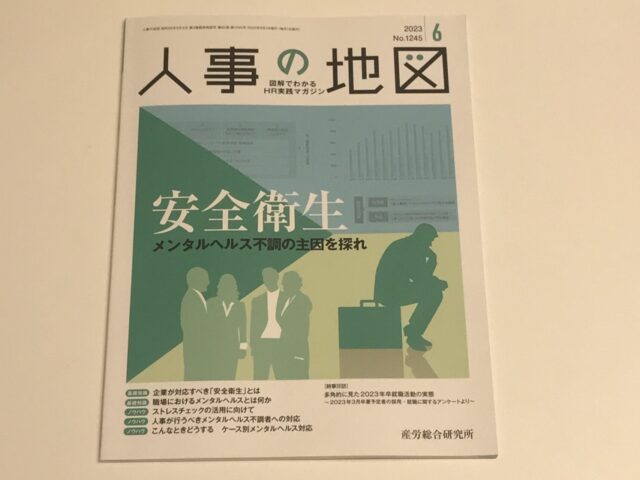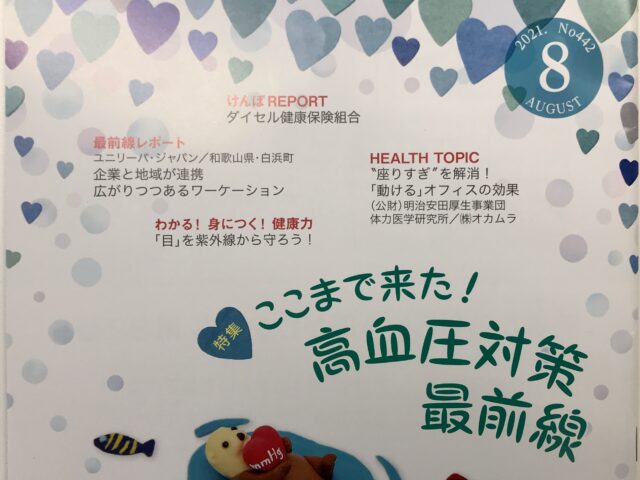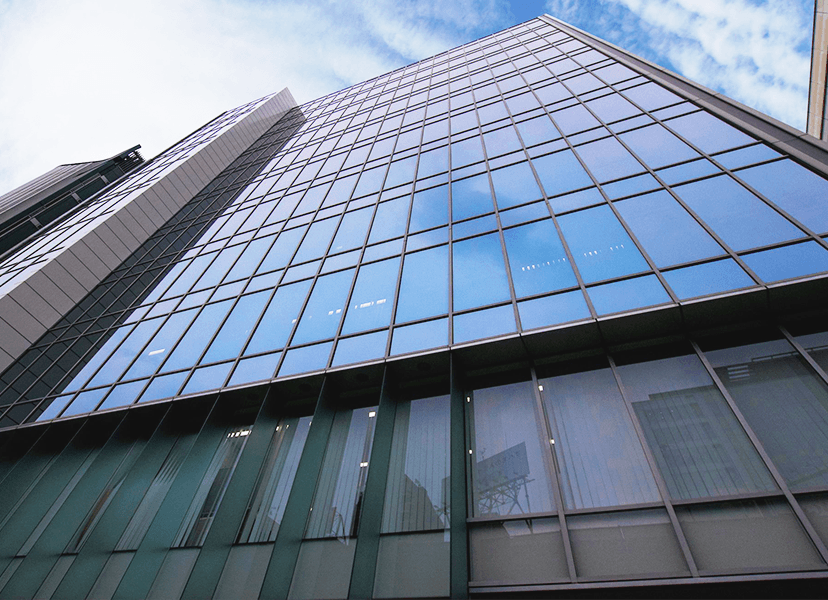Columnコラム

〜経営者が知るべき専門家の視点と実践ポイント〜
はじめに
2025年5月に「労働安全衛生法及び作業環境測定法の一部を改正する法律案」が正式に成立し、
2028年までにすべての事業場でストレスチェックの実施が必須となる見込みです。
これまで50人以上の事業所が対象だった制度が、いよいよ日本の全企業に共通の
“当たり前”となることで、
経営者には新たな責任が生まれる一方、
組織体質強化の大きなチャンスともなります。
本コラムでは、経営者がこの制度を活かすための視点を、
臨床心理士・特定社会保険労務士・公認心理師・産業カウンセラーといった
多様なカウンセラーの立場から整理し、実務上のヒントを具体的に提案します。
法令対応だけに留まらない、“人を大切にする経営”の実現に向けてお役立てください。
【1. ストレスチェック制度義務化の本質】
1-1. 制度の背景と社会的意義
社会・経済環境が急速に変化し、働き方改革やダイバーシティ推進が進む現代、
「こころの健康」は企業経営に直結する最重要テーマとなりました。
厚生労働省調査によると、職場のストレスによるメンタルヘルス不調は年々増加。
中小・小規模企業でも、休職、退職、労災請求といった深刻な事例が増えています。
全企業義務化は、こうした現場の“声なきリスク”から従業員を守り、
企業が社会的責任を果たすための土台を築くものです。
【2. 専門家が語る「経営者が持つべき視点」】
2-1. 臨床心理士の視点
「見えないストレスに目を向ける」
臨床心理士は、個人の心理状態やストレス反応を専門的に見立て、
カウンセリングや具体的な支援を行う国家資格者です。
<カウンセラーからの提案>
チェック結果は「一人ひとりが自分を見つめ直すきっかけ」として捉えましょう。
企業は「高ストレス者」だけでなく、全社員のストレス傾向に目を向け、
“未然防止”の姿勢を持つことが大切です。
一人で抱え込む社員を生み出さないために、一対一の対話の場や心理的安全性の確保が重要です。
2-2. 特定社会保険労務士の視点
「法令遵守と予防的労務管理」
特定社会保険労務士は、労働法令の専門家として企業の法的リスク管理を担い、
とくに労使トラブル・メンタルヘルス問題に関するあっせん代理も行える唯一の資格者です。
<カウンセラーから提案>
制度の形骸化はリスク。
「実施したこと」だけでなく、「結果をどう活かしたか」が問われます。
個人情報管理・同意取得・結果保存等、法的義務を正しく理解し運用しましょう。
チェック結果と職場環境改善の連動が不十分だと、
「安全配慮義務違反」「パワハラ・メンタルヘルス労災」への訴訟リスクが高まります。就業規則の見直しや産業医・外部専門家との連携体制も備えておきましょう。
2-3. 公認心理師の視点
「科学的エビデンスに基づく組織改善」
公認心理師は、心理学の知見を活かして個人と組織の両面から支援できる国家資格者です。
<カウンセラーからの提案>
ストレスチェックを「組織の健康診断」と位置づけましょう。
集団分析・傾向分析を活用して、職場ごとのストレス要因(人間関係、業務量、裁量度など)を見極め、
科学的根拠に基づく職場環境改善を推進しましょう。
「なぜこの部署だけストレスが高いのか?」など“データに基づく対話”を定着させることで、
組織の透明性と心理的安全性が高まります。
【3. 経営者が実践すべき具体的アクション】
3-1. 社内体制の見直しと専門家の活用
社内外の専門家(産業医・臨床心理士・公認心理師・産業カウンセラー・特定社労士など)と連携し、多角的なサポート体制を構築しましょう。
小規模事業所ほど、外部EAPやカウンセリングサービスの活用が有効です。
3-2. 従業員説明とプライバシー配慮
制度の目的・内容・個人情報の保護について丁寧に説明し、「不安」や「抵抗感」を払拭しましょう。
本人同意のない個人結果の閲覧禁止を徹底し、信頼関係を築くことがとても大切です。
3-3. チェック結果の活用とPDCA
毎年のチェックを「一過性」で終わらせず、集団分析→課題抽出→改善施策→効果検証のサイクルを回しましょう。
「高ストレス者」面談だけでなく、「職場全体の傾向や課題」に着目した組織改善を意識しましょう。
3-4. 管理職教育・ラインケア強化
管理職に対しては「ストレス反応の早期発見」「適切な声かけ」「相談窓口の案内」など、
実践的なメンタルヘルス研修を行うことが大切です。
「一人で抱え込まない」「気になることは早めに専門家と連携する」文化を浸透させましょう。
【4. 制度運用上の注意点とリスク管理】
4-1. 形骸化・アリバイ的運用のリスク
チェックの実施率や「やったこと」ばかりに目を向けると、制度は形骸化します。
結果を活かした職場改善・個別フォローがなければ、従業員の信頼も失われます。
4-2. 個人情報保護・同意管理
個人データの漏えい防止・適切な取り扱いは、法令上も厳格に求められます。
「本人の同意なくして面談指導や結果通知をしない」という原則を徹底してください。
4-3. 高ストレス者への支援と二次予防
高ストレス者には、専門家との面談機会を必ず提供しましょう(強制は不可)。
面談後の職場配慮や再発防止策も、専門家の助言を受けながらきめ細かく行いましょう。
【5. 「人を大切にする経営」への転換】
5-1. 企業価値向上のチャンス
ストレスチェック制度を前向きに活用する企業は、「従業員を大切にする会社」として社会的評価も高まります。
優秀な人材確保・定着、エンゲージメント向上、組織のイノベーションにも直結します。
5-2. 専門家連携で“人”が活きる組織へ
制度を「義務」ではなく「組織力強化のツール」と位置づけましょう。
臨床心理士・公認心理師・産業カウンセラー・社労士など専門家の知見を柔軟に取り入れ、多面的な職場支援体制を整えましょう。
【6. よくある誤解とQ&A(専門家アドバイス付き)】
Q1. 小規模事業所でも本当に必要?
→小さな組織ほど、一人のストレスや不調が全体に与える影響 は大きくなります。
顔が見える関係性を活かし、早期発見・早期支援がしやすいのが強みです。
Q2. どんな時に法律トラブルになる?
→制度を形式だけで終わらせたり、個人情報保護を怠ると、
安全配慮義務違反やプライバシー侵害で訴訟のリスクが高まります。
実効性ある運用を心がけましょう。
Q3. 相談窓口や外部リソースの活用は?
→社内に心理相談のプロがいなくても、
外部EAPやカウンセリング窓口の導入で
十分に対応可能です。
『いつでも相談できる』安心感が職場定着を促します。
Q4. チェックの結果はどう活かせばいい?
→組織全体の傾向をデータで可視化し、課題の“見える化”を進めましょう。
一時的な対応ではなく、継続的な職場改善サイクルを回すことが大切です。
【7. まとめ】
義務化を“成長の起点”にストレスチェック制度の全企業義務化は、
経営者にとって大きな“責任”であると同時に、
これからの時代を生き抜く“競争力”の源泉でもあります。
「やらされる」制度から「活かす」制度へ。
健全な職場づくり・働きがいのある会社づくりにぜひ挑戦してください。
“人を大切にする経営”こそが、御社の未来を拓きます。
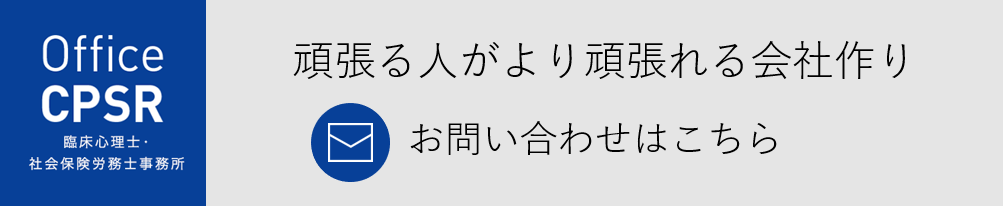
テレワークで困ったときに読む本 設計・運用・メンタルヘルス対策(中央経済社)好評発売中

※画像をクリックいただくとAmazonにて購入することができます。
※先輩に聞いてみよう! 臨床心理士の仕事図鑑(中央経済社)好評発売中
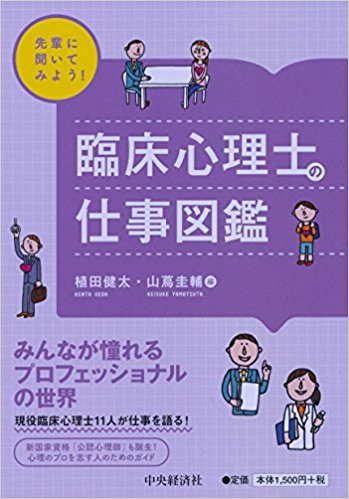
※画像をクリックいただくとAmazonにて購入することができます。
※図解ストレスチェック実施・活用ガイド(中央経済社)好評発売中
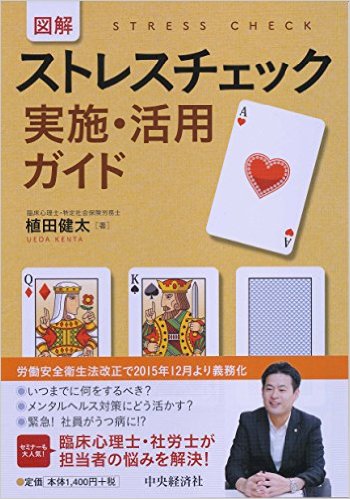
※画像をクリックいただくとAmazonにて購入することができます。
※なぜストレスチェックを導入した会社は伸びたか?(TAC出版)好評発売中
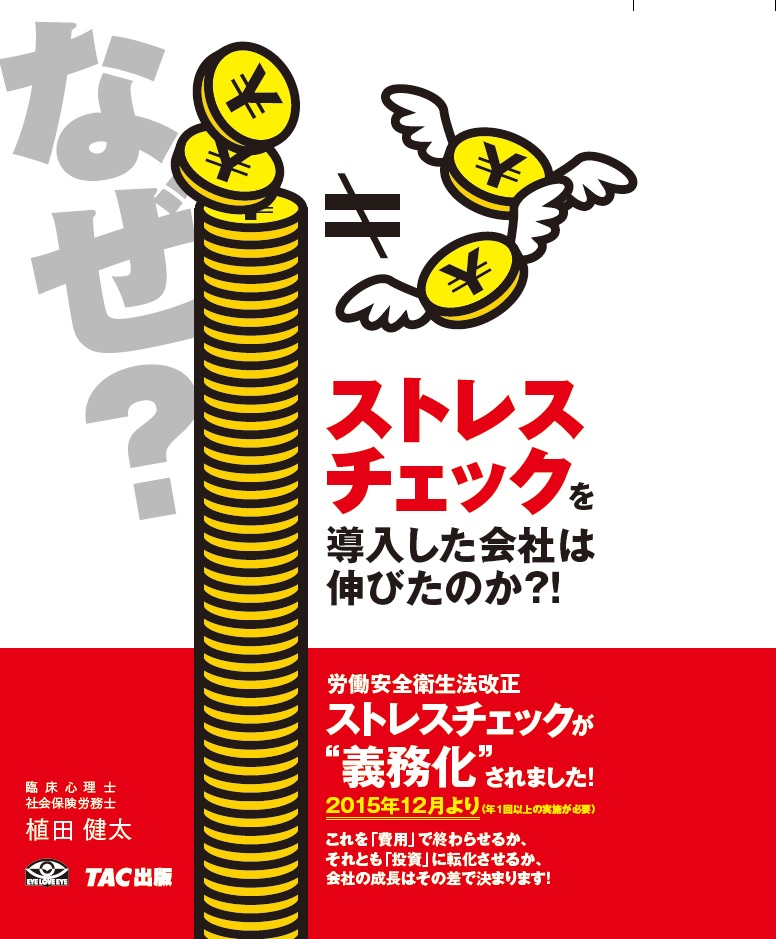
※画像をクリックいただくとAmazonにて購入することができます。
※公認心理師必須センテンス(学研メディカル秀潤社)好評発売中
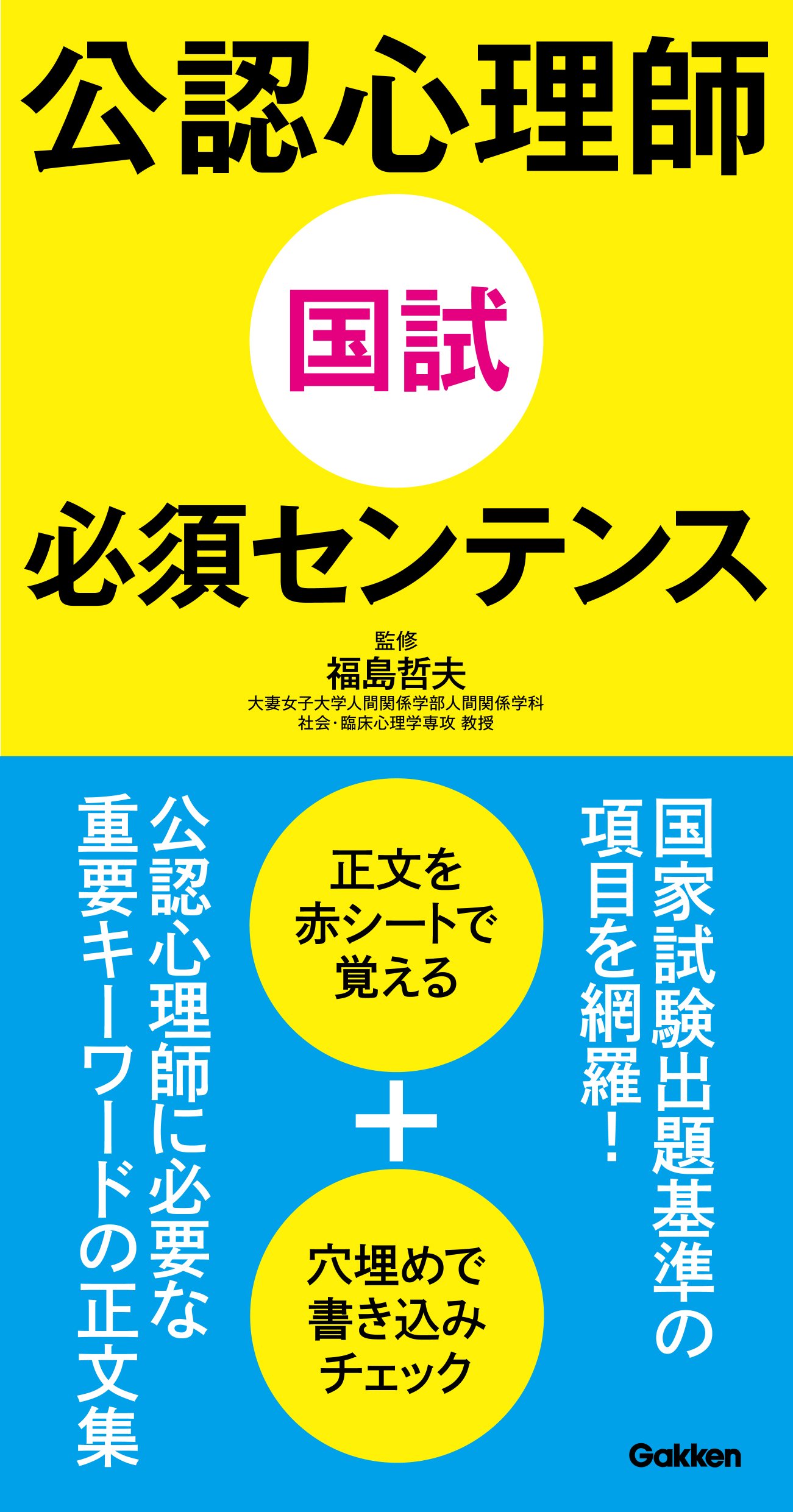
※画像をクリックいただくとAmazonにて購入することができます。
ストレスチェックQ&A まとめページはこちらから。
ストレスチェック制度Q&A冊子を
無料プレゼント実施中です。
下記資料請求フォームよりお申し込みください。
お問い合わせ
各種ご相談承ります。お気軽にご相談ください
受付時間 9:00 - 18:00 [平日]
Contactメンタル不調ゼロを目指すと逆効果【経営者向け】
休職中の部下に連絡してよいか【管理職向け】
仕事がうまくいってないなと気づいたときにやりたいこと【全ての働く人向け】
明星大学公認心理師インターン受け入れ
部下を承認している上司の見分け方【経営者向け】
メンタル不調ゼロを目指すと逆効果【経営者向け】
休職中の部下に連絡してよいか【管理職向け】
仕事がうまくいってないなと気づいたときにやりたいこと【全ての働く人向け】
ストレスチェック制度全企業義務化にどう向き合うか
Pick up